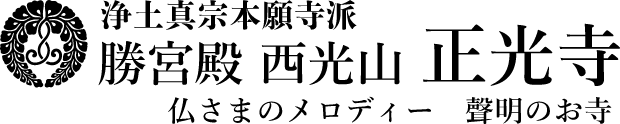第27代住職 大八木正雄
住職閑話
2025.09.01 1日240時間
大きな注目を集めつつ閉幕が近づく大阪・関西万博。そのテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」です。ちなみに55年前の大阪万博は「人類の進歩と調和」。いずれも未来に希望を抱かせる言葉です。その55年前の万博で上映された映画『1日240時間』が、いま静かに再注目されています。
題名も風変わりですが、内容はさらに奇抜です。研究所の博士と助手が、人間の活動速度を十倍にする薬〈アクセルチン〉を開発するのです。薬を飲めば仕事はたちまち片づき、余暇も充実。釣り堀は大盛況、助手は一人でキャッチボールを楽しみます。しかしボクサーが服用すると、速すぎて試合にならず、ついには身体がもたなくなってしまう……。映画は「効率化すれば幸せになるはずが、必ずしもそうではない」と皮肉を込めて問いかけています。
現代もまた、効率化の波がとどまることを知りません。新幹線は鹿児島から北海道まで走り抜け、スマホは目覚ましから決済まで生活に入り込みました。やがてはリニア新幹線が開業し、ますます距離も時間も縮まってゆきます。いつかは月へ日帰り旅行、などという時代も来るかもしれません。
しかし、効率化には人と人との関わりを失わせる危うさもあります。たとえばスーパーの無人レジ。便利ではありますが、「今日は寒いですね」と声をかけてもらった一言に心が和らいだ経験もあるはずです。教育の場では成果ばかりが優先され、介護や医療の現場では安心や温もりが後回しにされかねません。
問題は効率化そのものではなく、「何のために効率化するのか」という目的を見失うことにありそうです。効率を高めることは大切かもしれませんが、そのために人と人が支え合い、弱さを補い合う関係が損なわれては本末転倒です。そこにあるのは「目的なき効率化」がもたらす分断の危うさです。
効率化はあくまで手段にすぎません。その先にある「共に生きる」という目的を見失わないでほしいのです。朝の挨拶や、見知らぬ人との小さな譲り合い。そうしたふれあいこそ、人生を豊かにしてくれるものです。仏教はそのふれあう関係を「縁」といい、最も大切にしてきました。この「縁」を通して効率化を考えるとき、そこに「いのち輝く未来社会」が開けるのではないでしょうか。
55年前の言葉「人類の進歩と調和」。その響きは、今を生きる私たちに「共に生きる」という未来の方向をあらためて示しているのです。