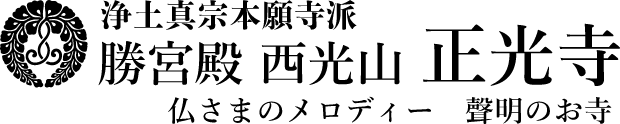第27代住職 大八木正雄
住職閑話
2025.08.03 澍法雨(じゅほうう) -はたらきバチに想う-
夏の暑い盛り、拙寺の庭にある手水鉢(ちょうずばち)には、朝から夕方までアシナガバチが水を汲みにやってきます。どこからか飛んできて、手水鉢の水をお腹いっぱいに飲んでは、ふらふらと巣へ帰っていきます。それを、何度も何度も繰り返しているのです。そう、彼らは喉が渇いたから水を飲んでいるのではありません。巣にいる女王バチや幼い蜂たちに水を届けるため、何度も巣と手水鉢を往復しているのです。まさに、「はたらきバチ」と呼ばれるゆえんです。
このはたらきバチたちは春に生まれ、女王バチのために巣を広げたり、幼虫にエサを運んだりして働きます。夏のあいだじゅう、仲間と協力して巣を守り、子育てに励み、やがて秋になると新しい女王バチが誕生し、はたらきバチたちはその役目を終えて、冬の前に命を終えるのです。一生懸命に働いても、これといった報いがあるわけではない…そんな一生です。
そんな、少しせつない彼らの姿を見ていると、「なぜ、彼らはあんなに一生懸命に働くのだろう」と考えてしまいます。人間は、とかく損得で物事を評価しがちです。だから、どれだけ頑張っても報われない彼らの姿は、「損な人生」と映ってしまいます。中には、「頑張って女王バチになれ!」とエールを送る人もいるかもしれません。
私たちのまわりには、自然のままに生きている虫たちがたくさんいます。しかし人間は、それらに価値をつけ、「益虫」「害虫」と区別したり、ときに「虫けら」などと呼んでさげすむこともあります。同じように、人間に対しても、「あの人は悪い人だ」「あの人はいい人だ」と言ってまた分けてしまう。しかも厄介なことに、自分が「悪い方」に分類されたときには、怒ったり、悲しんだり、心を乱したりと…。
自然は、互いに助け合い、補い合いながらバランスを保っています。勿論人間もその一部なので、せめて人間どうしだけでも互いに認めあう生き方ができればいいのですが、どうも難しそうです。好き、嫌い、憎い、うとましい、等々、人間を煩わせる“たね”は尽きません。
だから、仏教が説かれました。お経には「澍法雨(じゅほうう) 法の雨を澍(そそ)ぐ」とあり、仏の教え(法)は、雨 のように私に澍がれているということです。その雨の中に、亡き方々、ご先祖のお心を伺うことができます。私たちに、「互いに認めあう生き方をしてほしい」との願いが澍がれているのです。
のように私に澍がれているということです。その雨の中に、亡き方々、ご先祖のお心を伺うことができます。私たちに、「互いに認めあう生き方をしてほしい」との願いが澍がれているのです。
仏さま、ご先祖様の願いに気付き、自分の心を見直してみる。お盆を迎える大事な意味の一つです。
酷暑お見舞い申しあげます