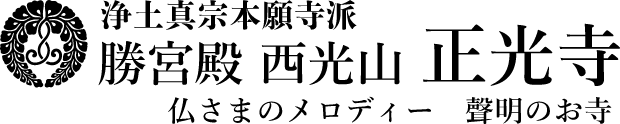第27代住職 大八木正雄
住職閑話
2025.10.02 蓼(たで)食ふ虫
このタイトルは、谷崎潤一郎(1886年~1965年)の小説名です。霞がかかったような文体で、複雑な男女の心模様を描いています。題名は、よく知られたことわざ「蓼食う虫も好き好き」から取られたものです。
このことわざは、江戸時代の狂言台本『縄綯(なわない)』に登場します。ある男が縄を綯いながら近所の人と話しています。「どこの家の嫁は醜い」「あの女は意地が悪い」など、他人の家庭や夫婦の悪口を並べ立てます。最後に「結局、人の好みはそれぞれ違う。蓼食う虫も好き好きだ」とまとめられ、笑いに転じます。『日本国語大辞典』も、この場面を初例として挙げています。つまり、苦みのある蓼を好む虫がいるように、自分には理解できない相手を好む人もいる、という好みの多様性を表す言葉といえるでしょう。
ところが、狂言の軽妙さに比べ、小説『蓼食ふ虫』ははるかに複雑で重い印象を与えます。これは、美味しいものではなく「蓼」を食べざるを得ない人びとの心模様を描いているからです。第三者から見れば「好き好きだね」で済むことも、当事者にとっては苦みに似た感情を抱えながら生きざるを得ない状況にあることもあります。小説全体に漂う「虚無感(生きる意味を見失った感覚)」の中に、その迫力がにじみ出ています。
日本人が大好きといわれるカレーライスも、嫌いな人はいます。たとえば俳優の速水もこみちさんや、元巨人軍の元木大介さんはカレーが苦手だそうです。お二人から見れば、大多数の日本人に対して「蓼食う虫も好き好き」となるのでしょう。万人が美味しいと言える食べ物は、この世に存在しないのかもしれません。
同じように考えれば、人間関係においても、すべての人と円満に付き合えることなど決してありません。必ず好き嫌いがあり、ときには愛憎へと深まることもあります。その結果、辛い現実を受け入れざるを得ないことも少なくありません。しかし、そうした自分を振り返って「蓼食う虫も好き好きでは?」と問いかけてみれば、かえって自分を苦しめていたこだわりに気づくかもしれません。
もっとも、この言葉を他人に向かって使えば、誹謗と受け取られることもあります。むしろ、自分自身が「蓼食う虫も 好き好きだったんだ」と気づかされるところに、深い人生観が生まれてくるように思います。多少の開き直りを認めつつも、偏見やこだわりから解放された人生が開けてくるでしょう。善し悪しや好き嫌いは人それぞれ。その違いを認め合うところに、互いを生かし合う豊かな関係が育まれるのではないでしょうか。
好き好きだったんだ」と気づかされるところに、深い人生観が生まれてくるように思います。多少の開き直りを認めつつも、偏見やこだわりから解放された人生が開けてくるでしょう。善し悪しや好き嫌いは人それぞれ。その違いを認め合うところに、互いを生かし合う豊かな関係が育まれるのではないでしょうか。