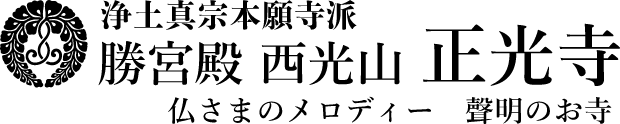第27代住職 大八木正雄
住職閑話
2025.11.03 もみじの離層(りそう)
拙寺のもみじも、夏の緑から少しずつ色を変え始めています。深紅に色を変えるもみじは、秋の大きな楽しみの一つです。
ただ、そこには不思議な自然の営みがありました。秋になって気温が下がると、もみじの緑色の葉は光合成ができなくなり、また冬の乾燥からもみじ自身を守るため葉を落とす準備に取りかかります。葉のつけ根に離層という壁を作り始めるのです。壁が作られ、葉の中で行き場の無くなった養分が日光と反応して紅くなり、あのもみじの輝きが生まれといわれています。そしてその反応が終わると、葉は役目を終え、静かに枝から離れていきます。
この離層という仕組み、どこか人間の老いにも似ています。人間の体力は、だいたい20歳代でピークを迎え、以降徐々に低下すると言われています。自身の経験で言えば、60歳を越えるとその低下のスピードは顕著となり、同時に気力も低下してゆきます。何となく覚悟を迫られているようで、私の心の中にも、離層が静かに育ち始めているように思います。
人間の離層の成長は、今はやりの「終活」とも共通点がありそうです。終活とは、身の回りの整理、財産相続の準備、医療介護の希望、葬儀お墓の準備などです。なるほど、どれもいのちを終えていくにあたり大切ですが、これらが準備できたとしても、もみじのように鮮やかに輝けるでしょうか。何かが足らない…。いのちの終わりが見えてきた人生で、輝かせる何かが。
それは、生きてきた意味(生きている意味)、そしていのちを終えていく意味が、きちんと見定められているかどうか、これがキーポイントではないかと思うのです。
お経に「独り生まれ、独り死に、独り去り、独り来たる」という言葉があります。私達の人生の誠に厳しい実相をあらわしている言葉です。ある高僧は、この句の前に次のような言葉を添えられました。
「相支え、相支えられつつ、独生独死独去独来」
私は、ここに人生の輝きを見ることができるように思います。
やがて、もみじが葉を落とし始めることでしょう。庭の掃除が忙しくなります。